こんにちは。ハリネズミです。
今回はこれまでのまとめ記事です。
「もっと手っ取り早く内向型のことを知りたい!」
「とりあえずこれ読めばわかるって記事が見たい!」
って人(いるかな??)に向けて書きました。
大まかな部分を説明しながら、細かな内容は詳細記事のリンクを貼ったので飛んでもらえればもと思います。
内向型の人の特徴
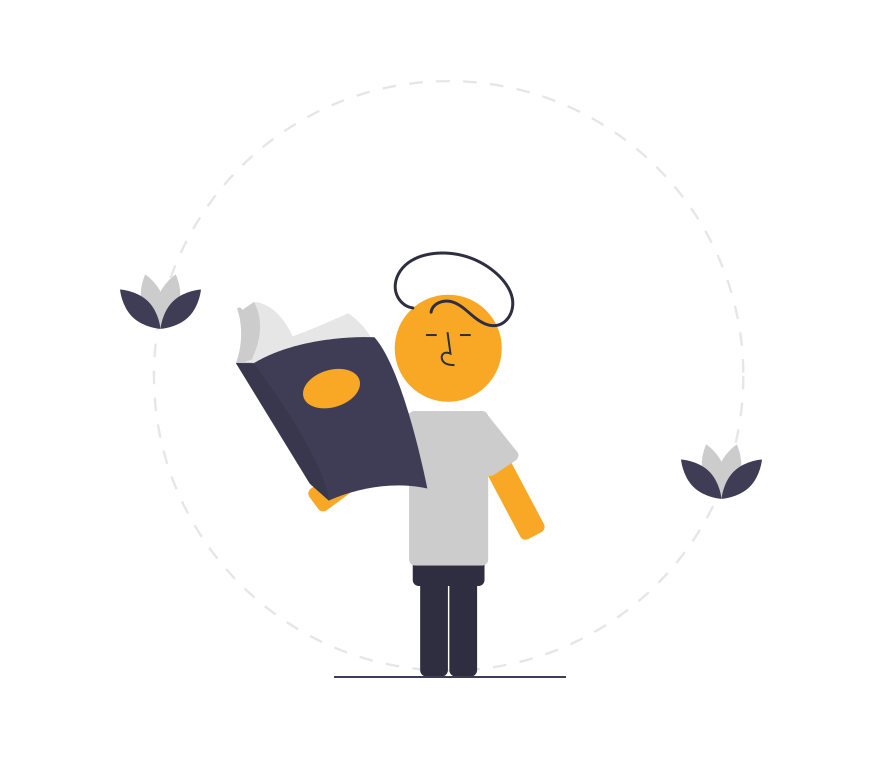
内向型の人の特徴をまとめると大きく以下の3つとなります。
- エネルギーを内から得る
- 刺激に対して感受性が高い
- 情報や経験は少なく、深く得る
この3つは全部関係しあっています。
内向的な人は一人の時間に考え事をすると元気がでてきます。
歩きながら好きな映画とかアニメの感動シーンを思い出したり、本を読んで自己研鑽してるとやる気湧いてきます。
また人と会ったり、大きな音が聞こえる環境だったり、注意を払う必要がある場所(人混みとか)にいると、刺激に対して敏感なため大きく疲れが出てしまいます。
 ハリネズミ
ハリネズミ僕は仲いい友達とも遊びに行ってもすぐ疲れちゃうんですよね。
そして外部からの刺激をできるだけ小さくするために、情報・経験数を絞ります。
厳選した情報・経験を深く考えていくことで次に生かしていくんです。



行動する「数」じゃなくて「質」で勝負していきます。


内向型の長所


内向型の長所についても、わかりやすく3つにまとめてみました。
- 分析力が高い
- 集中力がある
- 書くことが得意
内向的な人は起きている時、ずっと脳を働かせています。
今この記事を読みながらもいろいろと考えを巡らせているんじゃないでしょうか。
頭を常に巡らせて物事の因果関係を考えるクセがあるタイプの人が多く、これは分析力の高さと直結しています。
集中力が高いことも長所です。
特に一人で誰にも邪魔されない環境では、より長い間集中を保つことができます。
そして、話すことよりも書くことが得意です。
自分の考えを表現するときに一人でじっくり考えることができるからです。


内向型は遺伝によるものが大きい
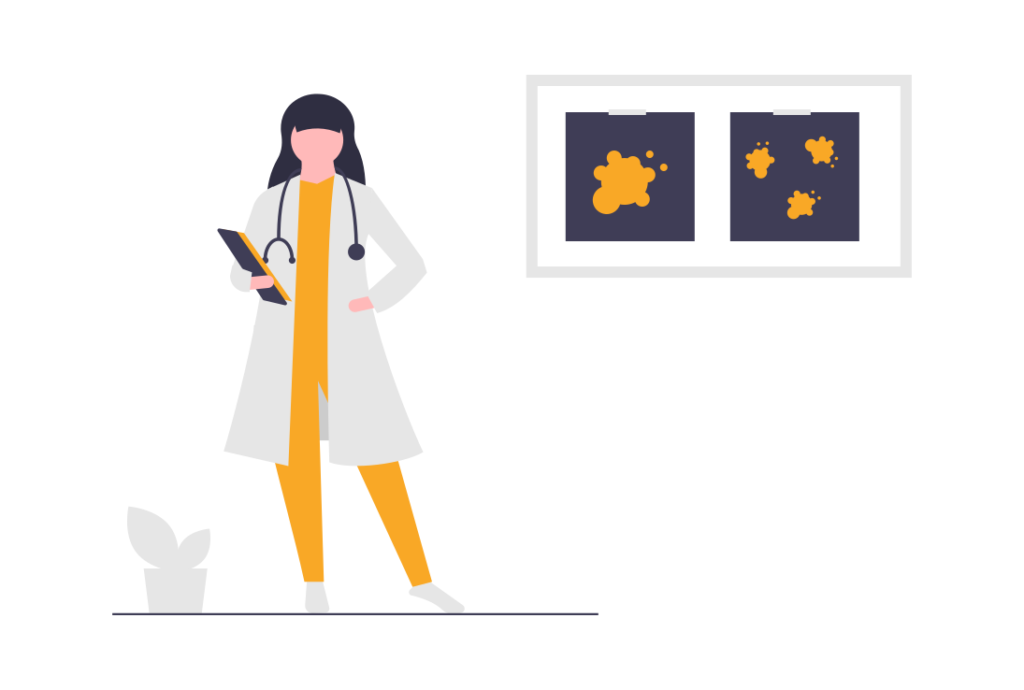
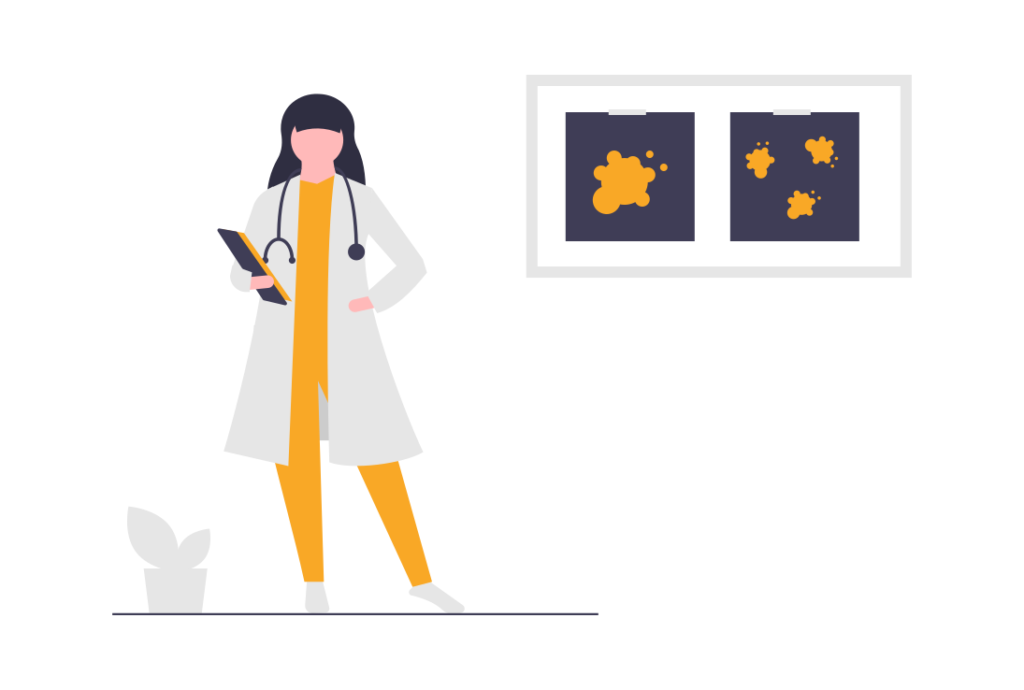
内向型を決める2つの遺伝子
結局のところ、内向型か外向型かは遺伝子によって決まっています。
- D4DR遺伝子 (新奇性追求遺伝子)
- SERT遺伝子
この2つの遺伝子が内向的か外向的かに大きく関わっています。
「D4DR遺伝子」が長いほど新しい刺激を求め、「D4DR遺伝子」が短いほど安定を求めます。
「D4DR遺伝子」が短いと内向型となる傾向が高いです。
「SERT遺伝子」はセロトニンの量に関わり、長さが短い場合、内向型になりやすいです。
神経伝達物質のちがい
脳の神経伝達物質にも違いがあります。
内向型・外向型は
- アセチルコリン
- ドーパミン
2つの神経伝達物質が大きく関与しています。
ざっくり言うと
内向型は「アセチルコリン」、
外向型は「ドーパミン」を使って脳を動かしています。
内向型はドーパミンの刺激に対する感受性が高く、刺激を弱めるためにアセチルコリンを使います。
ただドーパミンも必要で、ちょうどいいアセチルコリンとドーパミンのさじ加減がすごく狭いのが特徴です。


。
脳の仕組み
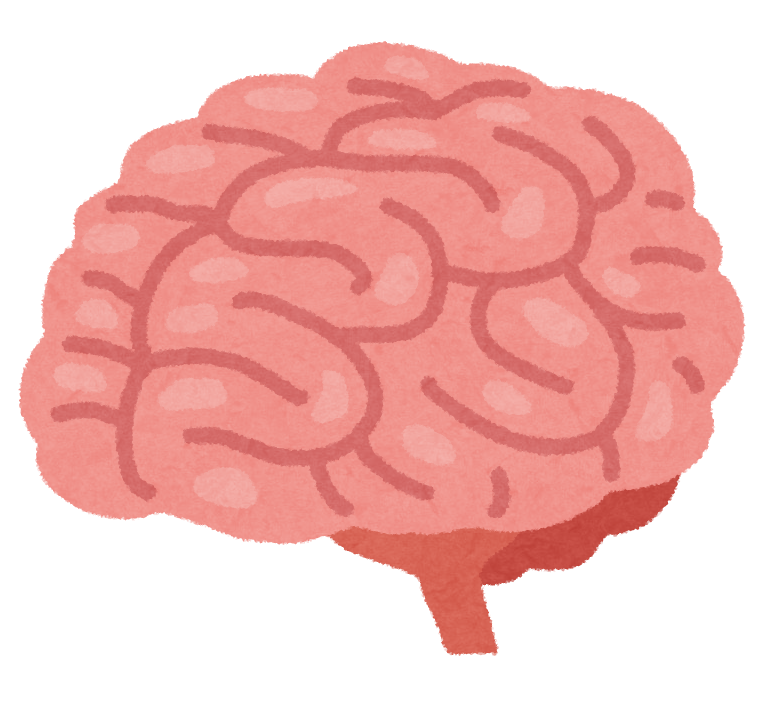
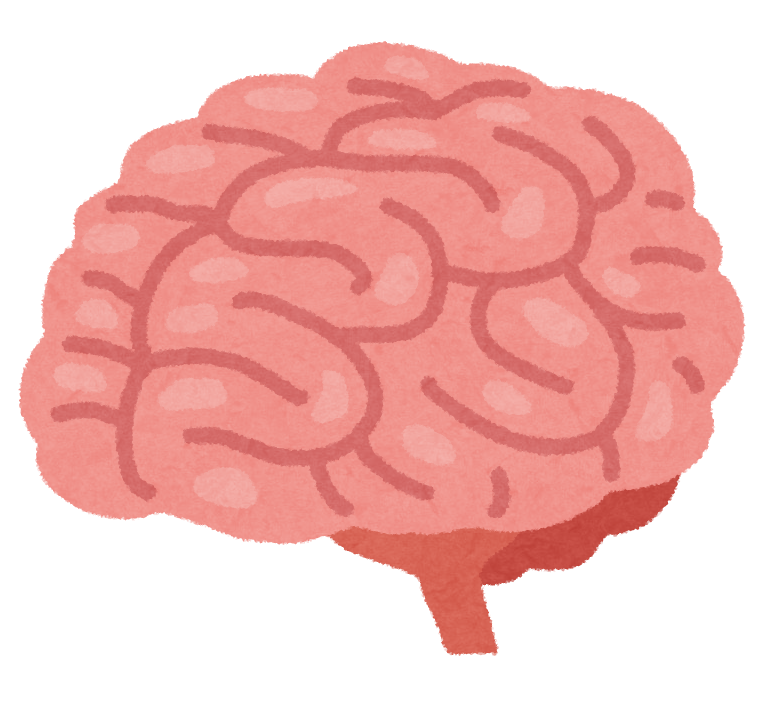
内向型の脳は前述したとおり、アセチルコリンを使って脳を動かしています。
このアセチルコリンの経路は長くて、ゆっくりと脳を動かします。
外向型の脳はドーパミンで動かし、内向型の脳と対照的に経路が短く、感情・運動をつかさどる部位を素早く動かします。
また、右脳優位型と左脳優位型でも得意・不得意の傾向が分かれます。
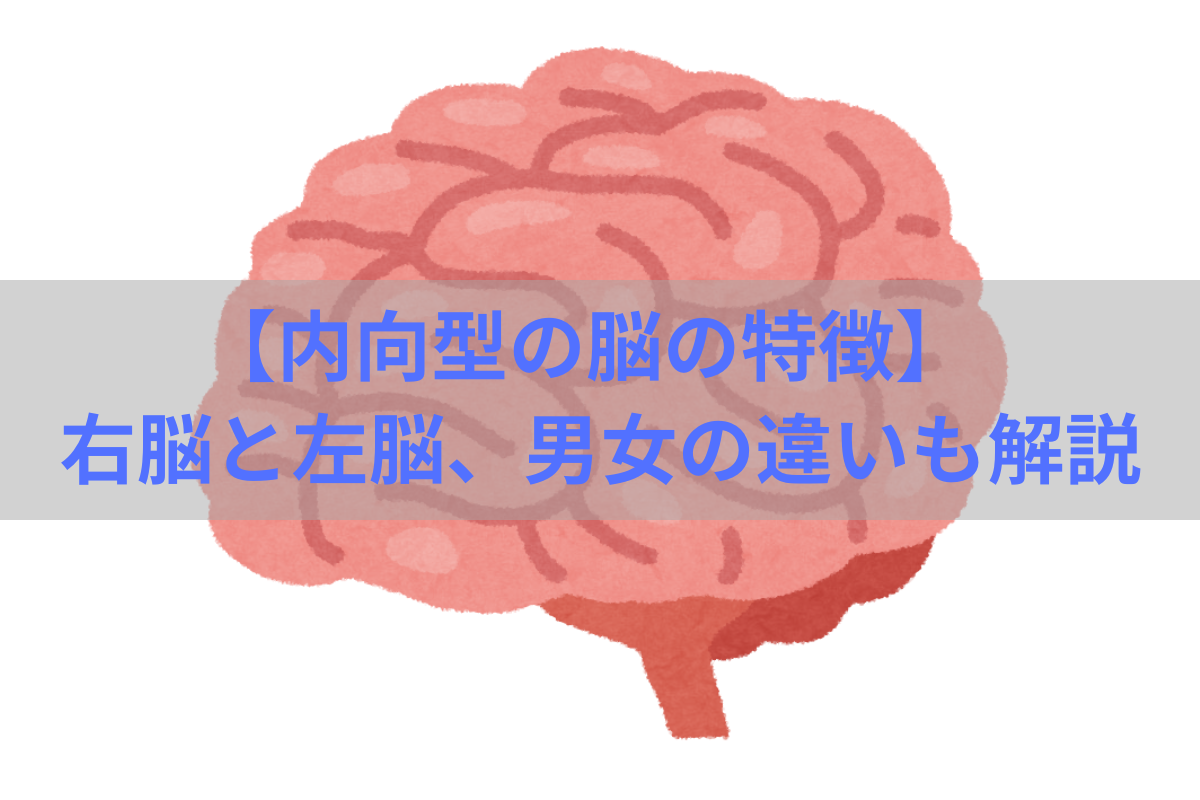
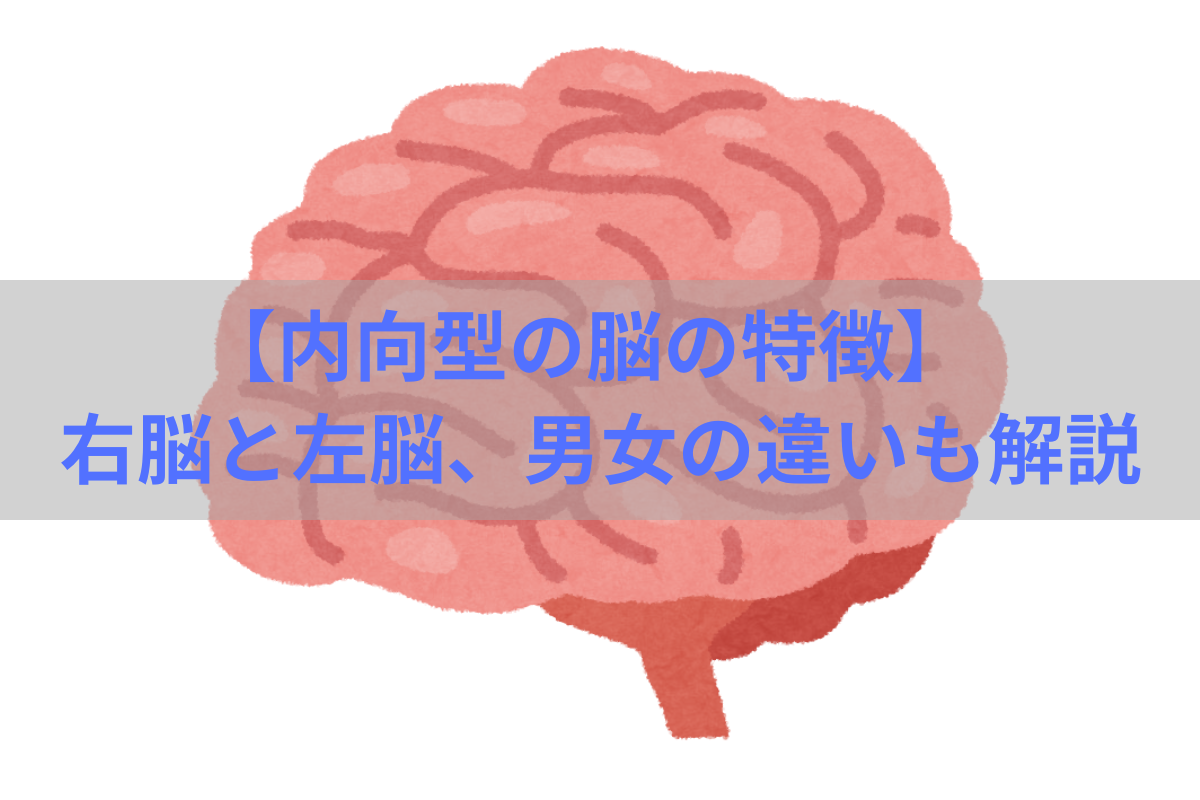
外向型が優位な社会


現代社会は外向型が優位に立てるようなシステムになっています。
組織の中に属して大勢の人がいる環境では、いろんな人に話しかけたり声が大きかったり
より多く発言する人の方が印象が良いです。
意欲的に何かに取り組む姿勢は高く評価されるし、正直うらやましくなってきます。
ただ、リーダーの素質は内向型にもあるんです。
ペンシルバニア大学の実験によると、内向型のリーダーは意欲的な部下をまとめる時に成果が高くなります。



僕の会社の社長はあきらかな外向型ですが、スタッフの意見をほとんど聞かなくて組織の意欲がどんどん下がる一方です。
またブログやSNSで、ひとりの環境で情報発信をすることができるようになり、書くこと・集中力が高いことに優れる内向型にとって優位な状況を作れるようになってきています。
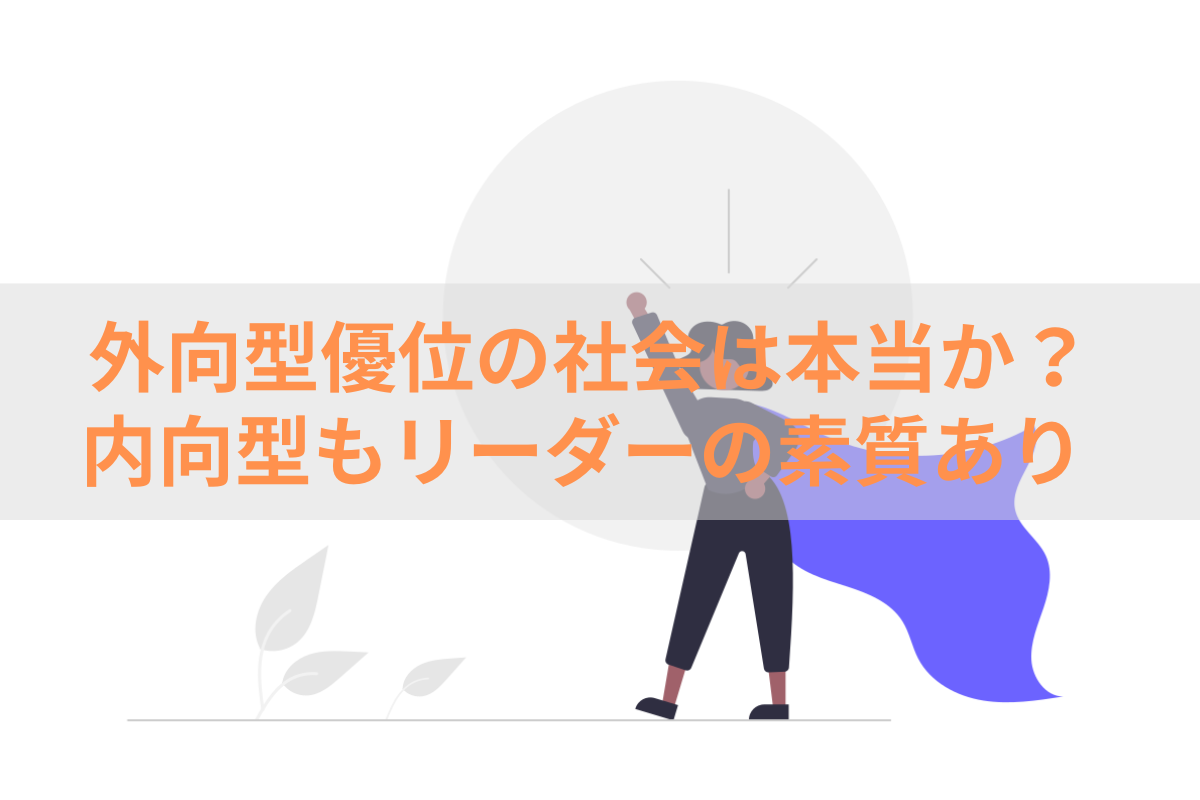
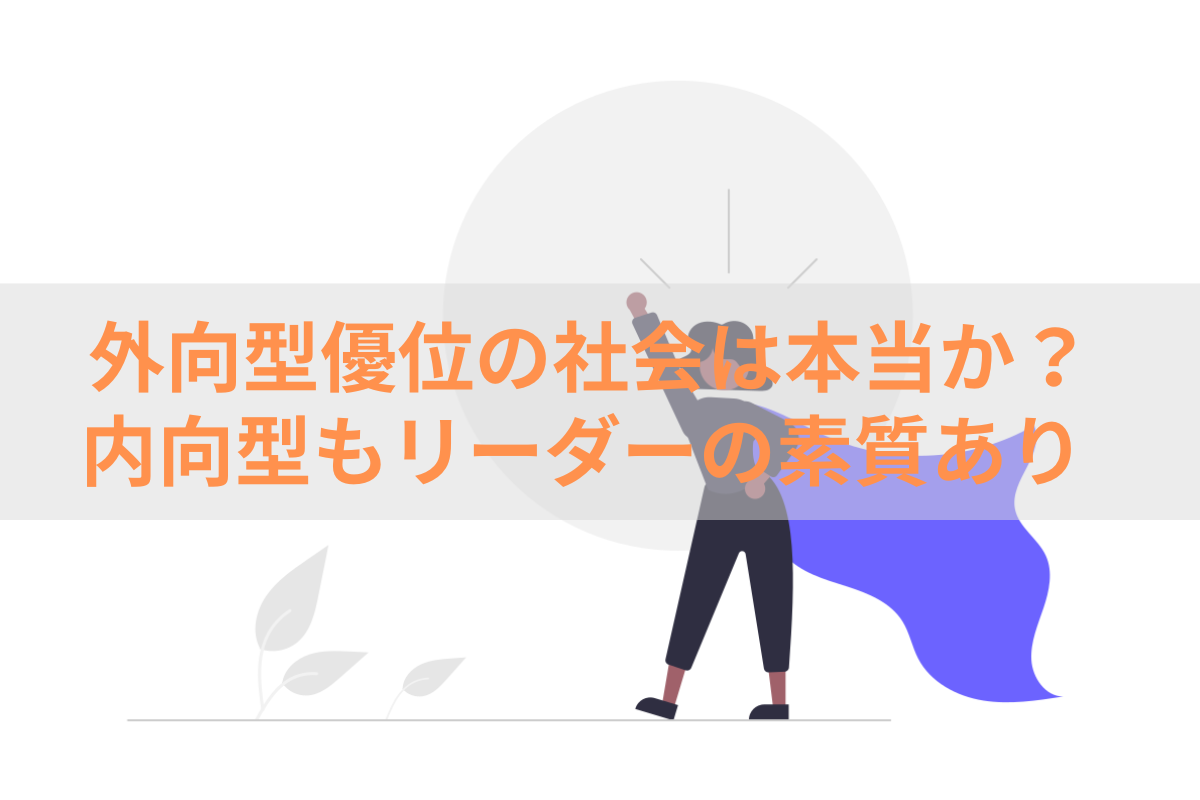
最後まで読んで頂きありがとうございます。
内向型を知ることは自分を知ることです。
自分を良く知る人こそ人生を良い方向へコントロールすることができます。
みなさんの人生が少しでもいい方向へ向かってくれたらいいなと思ってます。
それでは!!
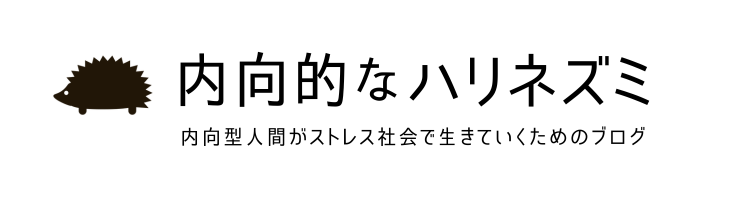
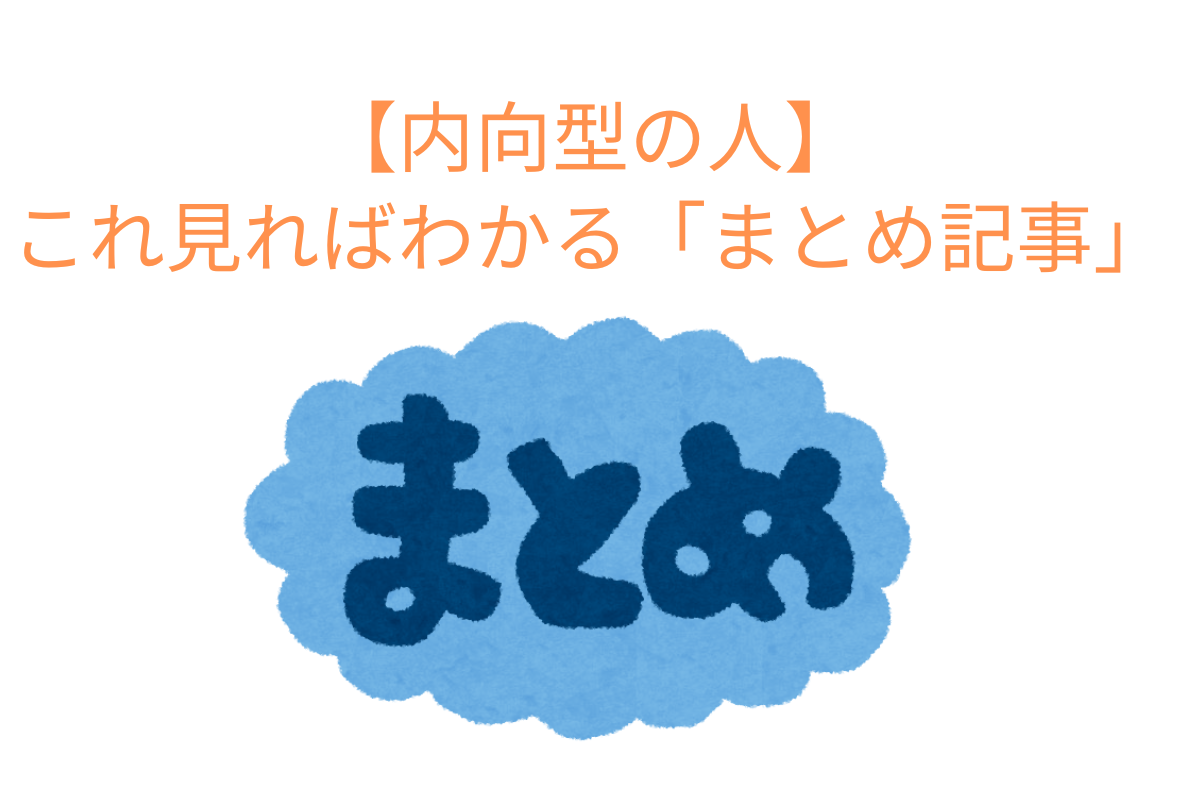

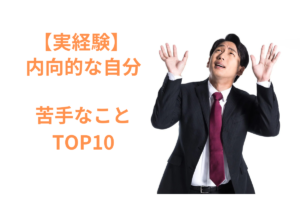
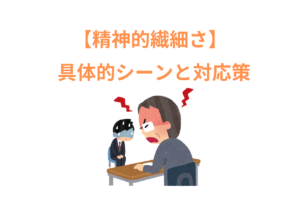
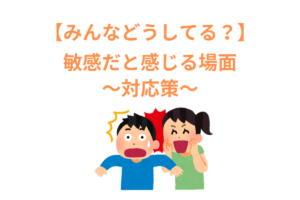
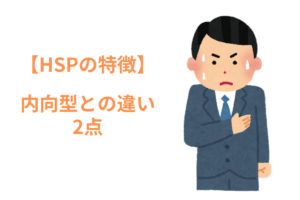
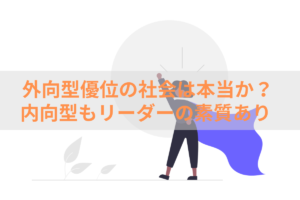
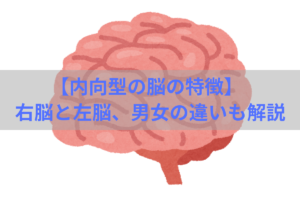

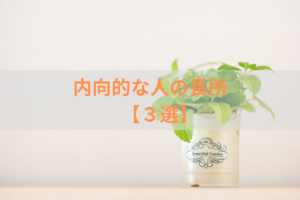
コメント